ケルティック・ハープで伝承曲を演奏しています。最近は、路上や公園のベンチでのんびり弾くことも多くなりました。
- /03 «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- » /05
|
|
自己紹介:
ケルティックハープで、ケルト民族の伝承曲を中心に演奏活動を行っています。
|
 |
|
| S |
M |
T |
W |
T |
F |
S |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
 |
|
 |
×[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
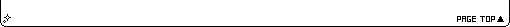 |
 |
音楽を演奏するときも聴くときも、その曲の世界をイメージします。
私は大体どこかしらで見た景色の記憶から、自分の頭の中で
新しい世界の物語を作っていくやり方をしています。
これは子供の頃から自然にやっていたことなのですが、
私が音楽から作る世界は深い自然に囲まれていることが多いのです。
そこで、今日ふと思いました。
どこに行ってもいつも自分の居場所がないような気になるのは、
自然しかないような場所に、私はまだあまり行っていないからなのかもと。
だから、ずっと音楽の世界が生まれる場所を探し続けているのかも
しれません。
東京のような都会やちょっとした観光地ではクラシック音楽の世界を
想像できる心境にあまりなれないとしたら、ヨーロッパの超不便な
自然に囲まれたような場所に行ってそこの土地から感じられるものを
吸収できたら、何だかどんどんいい音を作っていけそうな気がします。
札幌に数か月住んでみたけれど、雪がなくなった札幌に面白みを
感じられなくなってしまったのは、アスファルトの道を歩いても音楽が
自分の中で流れなかったからなのかなとわかったような気がして
きました。
雪で覆われた真っ白な世界では、イマジネーションがどんどん
膨らんだんですけどねぇ。
また、雪国に住みたいな~。PR
|
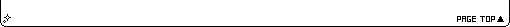 |
 |
ひさしぶりにシャルロット・チャーチ(の幼いころの天使の歌声)を聴いていたら
アンドリュー・ロイド・ウェーバーの『Pie Jesu』を歌っていて、ちょっと感動しま
した。
その流れでフォーレのレクイエムの『Pie Jesu』も聴き、あまりの美しさに溜息。
レクイエムとは鎮魂歌。死者の魂をなぐさめるミサ曲です。
ガブリエル・フォーレのこの曲はとても美しい旋律のため死の子守歌とも云われ、
演奏されることも多い曲です。
こんな意味の歌詞を歌い続けます。
憐れみ深き、イエズスよ
彼らに安らぎを与え給え
永遠の安息を
Pie Jesu Domine, dona eis requiem, dona eis requiem,
Pie Jesu Domine, dona eis requiem, dona eis requiem,
dona eis Domine, dona eis requiem,
sempiternam requiem,
sempiternam requiem,
sempiternam requiem,
Pie Jesu, Jesu, Pie Jesu Domine, dona eis, dona eis
sempiternam requiem,
sempiternam requiem.
この曲はやはり人気らしく、ネットで検索すればたくさんの人が記事を書いて
いるので、機会があったら読んでみてください。
アンドリュー・ロイド・ウェーバー版の『レクイエム Pie Jesu』を聴きたい人は、You TubeにUPされているヘイリーの歌なんかどうでしょうか。
ヘイリー...顔が変わった気がしますが、やせたのかな。
あ~ やせたのかな...のところで、急にスティーブン・キングの『痩せゆく男を やせたのかな...のところで、急にスティーブン・キングの『痩せゆく男を
思い出しちゃいました。呪いをかけられて手に穴が開くところが、苦手なんだよなー。手の平に穴をあけられて呪いをかけられるんだっけ...?
どっちにしても、こわいよ~。 |
|
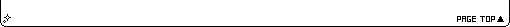 |
 |
|
きらきらひかるー おそらのほしよー
と歌われる『きらきら星』は、みなさんご存知でしょうか。
この曲は、18世紀に流行ったシャンソンだと云われます。
"Ah! Vous dirais-je, Maman" あのね お母さん』というのが
原題で、クラシックのコンサートなどで演奏されるときには
『ああ お母さん聞いてよ』と紹介されることもありますよね。
18世紀後半を生きたモーツァルトが、このシャンソンのメロディーを
変奏して、それが現代まで受け継がれ『きらきら星変奏曲』として
演奏されています。
子供の頃にヴァイオリンを習った人などは、必ずといっていいほど
この曲を習っていると思います。これを聴いて「美しい…」と感じ
ながら喜んで弾く子供はそうそういないと思いますけど、じっくり
聴いてみると心の琴線に触れる部分があったりします。
と書いたところで、よく使われる「心の琴線」という言葉について
考えてみたのですが、この言葉は辞書によると
「心の奥深くにある、物事に感動・共鳴しやすい感情を琴の糸に
たとえていった語」
だそうです。
ケルティック・ハープは竪琴の一種で、ハープという楽器は、
周囲の環境や設置物に大変共鳴しやすいのです。
「心の琴線」を英語で表現するときに、chord(コード=和音)と
いう単語が使われたりするように、心に触れるものが音楽に
関する言葉で表現されていると嬉しくなります。
私も、人の心に触れる音を奏でてゆきたいです。
|
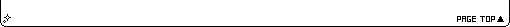 |
 |
昨夏乗って懲りた急行はまなすに、また乗ることになりました。
別の手段で札幌から東京に向かうつもりが、札幌で急用が入ったのでやむなく。
でも前に乗ったときと違って、シートのクッションがわりとしっかりしてたので助かりました。
札駅のホームではまなすを待っていたら、前に並んでいたおじいさんが後ろを振り返って
にっこりしてきました。なぜかこの晩、珍しく他人の話に乗った私。気をよくしたおじいさん
は(すでに酔っ払ってたみたいだけど)、お酒を買ってきて飲みなよと渡そうとするのです。
趣味でJRのおとく切符で旅行しまくってる人で、たまたま私が知っている鈍行の列車名の
話で共感したのか、楽しくやりたかったんだろうな。
ごめん。私はそこまでつきあってあげられる心やさしい女じゃないのよー、私と話しても
広がらないからつまらないしさ…。
ビールの500缶とワンカップのお誘いを断り、悪かったなぁと自己嫌悪に陥りました。
さすがに、電車の中で500のビールは…。
その後、青森から弘前回りの電車に乗った私は、うわーっという曲を聴きたくなり、
ベートーヴェンの交響曲をBGMにして東京まで戻りました。丸一日、ウィーンフィルの第九。
この曲を聴くと、人間が生まれてから味わう様々な世界が駆け抜けてゆく…ようなイメージが
わきます。
単純に、よくこんな曲を作曲できるよなーと感心仕切りの第九です
が、もちろんシラーの詩による歓喜の歌にも感動なのです。
ベートーヴェン、、、波乱に生きた人のイメージがあるけど、音楽に誠心誠意をこめて作曲に
懸けたんだろうな~。
|
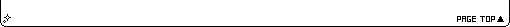 |
|
 
|
